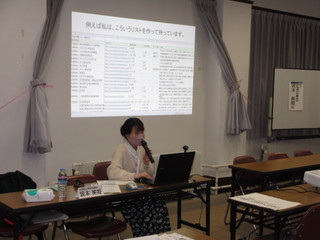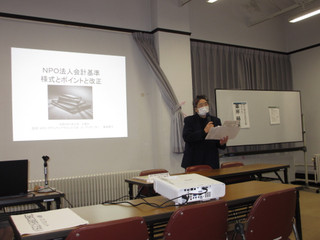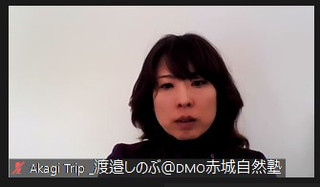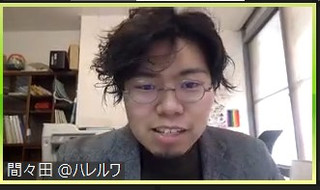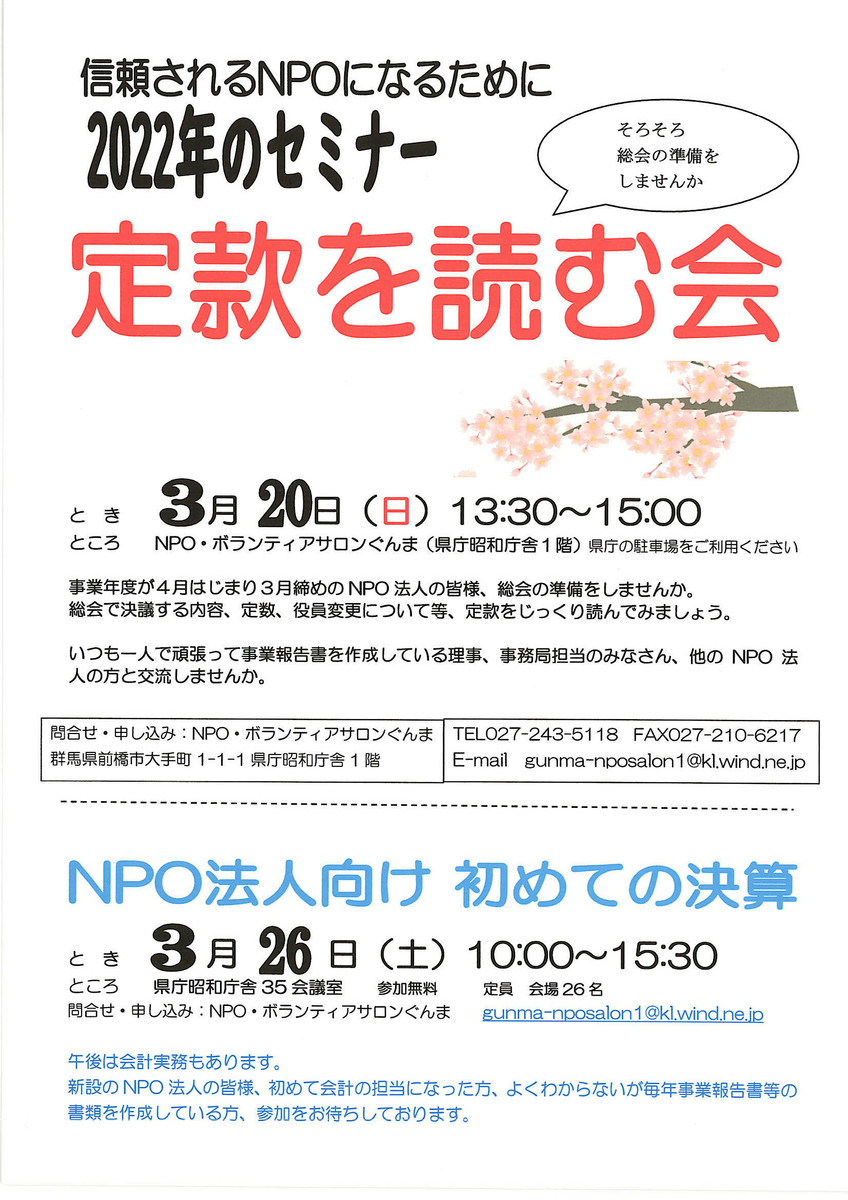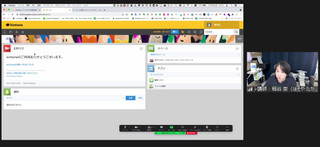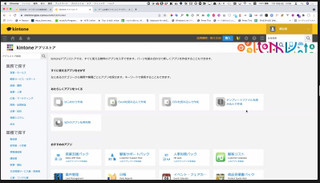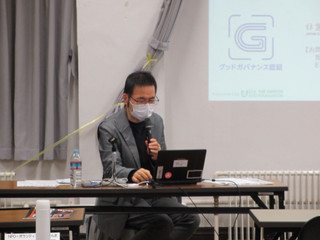2022年1月28日、zoomにて「資金調達のコツ クラウドファンディングセミナー」を開催しました。(新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、zoomでの開催となりました。)
参加者は35名でした。(NPO法人21名、中間支援スタッフ8名、行政職員2名 その他4名)
《内容》
クラウドファンディング(以下「CF」)をテーマにしたセミナーは今回が初めてということで、はじめにCFについての基本をお話し頂き、その後、県内でCFを活用した実績のあるNPO団体に、実際の事例を発表して頂きました。
第1部 クラウドファンディングとは
~クラウドファンディング成功のコツ 上毛新聞社読者局地域交流部 和田 亮介氏

まず、クラウドファンディングとは:CROWD (群衆)+ FUNDING(資金調達)
実現したいことや夢などをインターネットで配信し、多くの人から少しずつ支援金を募る仕組みで、様々なプラットフォームがある。
例:「CAMPFIRE」「READYFOR」「Makuake」など
サイトによって特徴、得意分野があるので、見極めて使い分けが必要。
◆クラウドファンディングのメリットは・・
・多くの人から手軽に資金調達ができる
・・群馬にいながらにして、日本全国から支援金を募ることができる!
・ファンづくり
・・プロジェクトが終わった後も継続的に関係を築ける!
・テストマーケティング
・・特に製品をつくる場合、リアクションを見ながら小出しにできる!
◆クラウドファンディングのデメリットは・・
・手間がかかる・・リターンの準備、HPの制作、発信をまめに
・未達成のリスクがある
・プロジェクトに責任が伴う
★上毛新聞社が運営する「ハレブタイ」について★
種類:購入型クラウドファンディング(オール・オア・ナッシング方式)
設定金額:特に制限なし
手数料:20%
募集期間:1週間~90日間
決済:クレジットカード、paypay、paidy
HP制作:上毛新聞社が制作(掲載内容の原案は起案者が制作)
いろいろな案件に携わってきた経験から・・
◆成功のポイント
1.刺さるストーリー
・内容はシンプルに・・あんなこともこんなことも、ではなく、目的を明確に。
・画像・動画が有効・・動画を上げると、達成率UP。動画は3-5分ぐらいが効果的。
・「ならでは」のリターン・・その人、団体、プロジェクトならではのユニークなリターン。
2.周到な準備
・経費・労力の計算・・リターンの準備、情報発信など、一人でやるには限界がある。
・支援者リストアップ・・親戚など、身近な人から着実に。
・無理のないリターン
3. とにかく発信!
・なるべく大人数で・・一人では無理、役割分担を。
・こまめな活動報告・・ブログ形式で、活動の様子を随時アップする。
・他人任せは危険!・・役割分担はするけれど、まかせっぱなしはダメ。
★「ハレブタイ」の特長としては・・
・新聞記事でプロジェクトを紹介してもらえる!
・地元活性化との親和性があり、ビジネスと差別化できる!
・なんといっても信頼感!
→様々なサイトがあるので、各サイト上で過去のプロジェクトを見て実績を研究し、
最適な運営サイトを選ぶことが大事
第2部 クラウドファンディング事例発表
①NPO法人 赤城自然塾 ~AKAGI e-Bike(赤城山e-Bike レンタル&サイクリングツアー)
事務局次長 兼 コーディネーター 渡邊 しのぶ氏
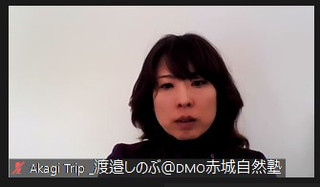
まず、団体の紹介。「NPO法人 赤城自然塾」は官公庁登録の観光地域づくりDMOになっている。
2021年度からはDMOエリアの前橋市・桐生市に加え、渋川市・みどり市の4市の協働で、沼田市・昭和村の協力も得て、自転車をキーとした観光地域づくりに取り組んでいる。
「AKAGI e-BIKEコミュニティレンタサイクル」
2018年度群馬県の地域・まちなか活性化応援事業にエントリー、優秀事業プランに選定
→「ハレブタイ」を活用して、CFに挑戦
→目標金額50万円達成、支援者78人
https://greenfunding.jp/harebutai/projects/2631
よかったこと
・アンカンミンカン富所さんがリターンに協力してくれた
・上毛新聞で紹介してもらうことで多くの人に活動を知ってもらえた。
・今まで繋がりのなかった赤城山地域の企業やお店から支援を頂いた。
わかったこと
・観光という要素は、共感を得にくく、CFには不向きだと感じた。
・CFを通じて地域の人に知ってもらうということも目的の一つで、ある程度は達成された。
・CFはサイトに掲載するだけでなく、SNSなどを活用して状況報告等をマメに行うこと、
また、実際に自ら足を運んでお願いをすることが一番有効。
情熱=走り続ける気持ちと、マメさが大切!
支援してくださった方
・仕事で関わっている仲間や地域で関わっている方々から多く応援、ご支援頂いた。
②NPO法人 居場所づくりサポート~samiitosu カフェスペース新サミートスの再開
代表 今田 裕子氏

まず、団体の紹介。2015年から活動を開始、地域の居場所として4つの活動(①給食カフェ ②カフェとして居場所提供 ③子ども食堂・キッズルーム ④個別指導・自習室)を展開していたが、2020年8月、コロナ禍で活動を継続していくことが困難になり、家賃の支払いも難しくなりやむなく閉店。活動拠点を縮小し、再始動を目指す。
2020年11月 CFサイト「GoodMorning」にて新たな居場所の改修費を募る。
「未来を担う世代の居場所を高崎から。お腹も心も学びも、丸ごとサポート」
→目標金額100万円達成、支援者102人
→2021年4月リニューアルオープン
https://camp-fire.jp/projects/view/333564
工夫したこと
・SNSの活用(HP、ブログ、Facebook等、くりかえし状況を発信)
・確実に支援してくれる方には、事前に直接依頼(スタート直後の金額を増やすため)
・賛助会員に手紙で直接依頼(CF開始後、2週間後に送付)
・直接現金で寄付を受け取った場合も、すべてCFに入金
わかったこと
・手紙が一番効果的。
・CFのやり方がわからない人も多数いて、直接現金で受けとることも。
・CFをしたことが、新店舗周知させるきっかけとなった。
支援してくださった方
・もともとの賛助会員が6割、もともとのお客様が2割、友人知人が1割
CFで初めて活動を知ったという方は1割弱
③ハレルワ ~コミュニティスペース「まちのほけんしつ」立ち上げ
代表 間々田 久渚氏
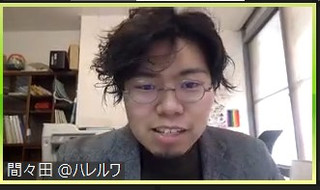
まず、団体の紹介。ハレルワは、2015年に発足したLGBT・セクシュアルマイノリティ支援団体。交流事業、啓発事業、居場所事業、相談事業を行っている。
交流事業として月1回交流会「ハレの輪」を行っていたが、常設のいつでも来れる保健室のような場所をまちなかにつくれないかと考え、物件をさがしていたところ、不登校・ひきこもり支援をしている「アリスの広場」と出会い、共同で「まちのほけんしつ」を開設することに。
2019年度群馬県の地域・まちなか活性化応援事業コンペに参加
→「READYFOR」を利用してCFに挑戦、「まちのほけんしつ」開設にあたって改修工事に必要な費用を募る。
→目標金額120万円達成、支援者214人
→2021年7月 構想から2年越しで「まちのほけんしつ」をオープン、感謝祭(オンライン)
https://readyfor.jp/projects/matihoke
工夫したこと
・新聞・ラジオなどのメディアで積極的にPRした。
・担当者を決めてスケジュール管理した。
・進捗ブログやカウントダウン、達成後もシステムを活用している。
・応援メッセージやリターン品で外部のいろいろな人を巻き込んだ。
支援してくださった方
・群馬県のみならず、北海道から九州まで全国19都道府県から、総勢214名の方から支援を頂いた。
第3部 登壇者によるトーク・質疑応答
ファシリテーター 上毛新聞社読者局地域交流部 和田亮介氏
◆今後CFを考えている団体へのアドバイスは?
→「折れない心」が大事、「お金ください」とお願いするのは大変なこと。あとは、「マメさ」(NPOの活動全般についていえること) 〈渡邊さん〉
→思っていた以上に大変だったが、やってみていろいろなことがわかった。身近な人ほど寄付してくれない、とか、普段のお客さん(利用者)には活動の大変さが伝わってない、とか。良い面としては、学生などいろいろな人が活動を知ってくれるきっかけになった。カフェが復活して、不登校の子が来て結果的に居場所になったり、必要とされている、やってよかったと実感。やはり寄付文化は日本ではなじみがないのかな、という印象。 〈今田さん〉
→自分たちの団体にとってはCFは有効な手段だった。大変だったけど、またやるかも。手数料が高いという意見もあるが、フルサポートで安心な面はあった。 〈間々田さん〉
◆全く繋がりのない方からの寄付の割合は?
→1割いないぐらい。〈間々田さん〉
→1~2割いかないぐらい、まだ知らない人に活動を届けるには有効〈渡邊さん〉
◆目標未達で団体に支払われない場合は、そこまで集まった寄付はどうなるのか?
→「達成」になるまで、決済はされない仕組みになっている。
(達成された瞬間に支援者に通知が行き、決済されるシステム)
最後に和田さんから、3人の話を聞いて、CFは結局のところ「手紙」や「地道な営業活動」といったリアルな行動が大事で、関係性を築いて次の活動のサポーターになってもらうという働きかけを地道に行うという、普段の活動の延長が成果につながるというまとめがありました。