9月 パソコンお助けサロン
9月パソコンお助けサロンのお知らせです。
9月20日(木) 午後6時から
NPO・ボランティアサロンぐんまにて
今回はデジカメ動画で15秒の団体紹介CN作りを行います。
動画の素材はサロンでご用意いたします。

9月パソコンお助けサロンのお知らせです。
9月20日(木) 午後6時から
NPO・ボランティアサロンぐんまにて
今回はデジカメ動画で15秒の団体紹介CN作りを行います。
動画の素材はサロンでご用意いたします。
![]() NPO支援のための連続講座(第8回目)のお知らせです
NPO支援のための連続講座(第8回目)のお知らせです![]()
日 時: 8月28日(火)13:00~16:00
場 所: 県庁昭和庁舎2F21会議室
講 師: 妻鹿ふみ子さん(日本ボランティアコーディネーター協会運営委員)
講座名:「コーディネートの力」
中間支援センタースタッフの支援力アップのために開催していますが、NPO団体で活動している方、関心のある方も参加できます。
講座終了後、NPO・ボランティアサロンぐんまで交流会を行います![]()
申込はこちらから↓
word.docxをダウンロード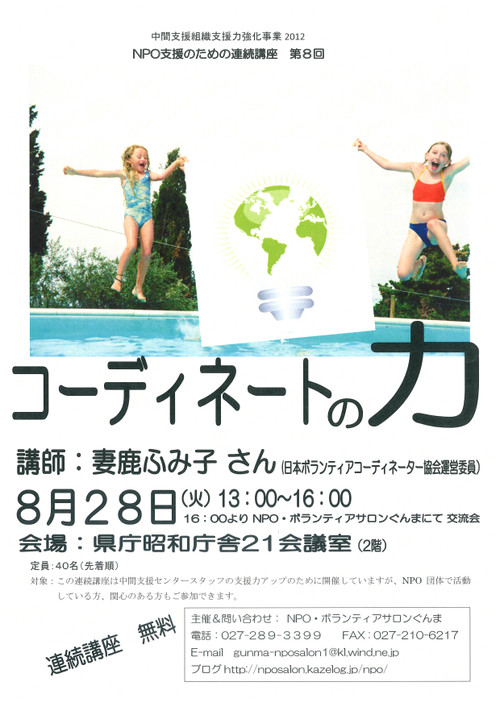
![]() 下記のリンクにとんで、 いいね!を押せば、そのまま購読できます
下記のリンクにとんで、 いいね!を押せば、そのまま購読できます![]()
市民力養成講座のお知らせです。
9月3日(月)19:00より、「NGOから学ぶ資金調達術」と題して、星川淳さんの講演会を開催します。
資金調達というと、まず最初に助成金や補助金を連想される方もたくさんいますが、市民活動のミッションを本質的な意味で果たすためには、どこの干渉も受けない、どこからも制限を受けない、自由なスタンスが必要です。
そのためには自主財源率(会費・寄付・事業収益)を高め、他主財源率(助成金・補助金・委託金)を低くしていく必要があります。
公的な委託や補助金に頼れないNGO。しかし、自主財源をもとに、職員の人件費も確保し、自立的な活動を推し進めている団体があります。
2005年から5年間、海外NGOの事務局長を務め、2010年より一般社団法人アクト・ビヨンド・トラストを設立した星川淳さんから、NGOの経験を民間団体の設立・運営にどのように生かしているのか、日本での現状を踏まえながら、お話しいただきます。
申込はこちらから↓
4月からファミリーボランティア(お花に水をあげよう)を実施しています。
今日は雨で、水やりはできませんでしたが、44人と多くの子ども達に
お越しいただきましたので、読み聞かせのみですが紹介します。
読み聞かせは、サロンの赤石と峯岸です。



最初は赤石が「おばけのがっこうへきてください」を、
そのあと、子ども達のアンコールに応えて「はらぺこあおむし」を。
大型絵本を二人で劇をするように。大好況でした。下記をクリックし動画でご覧ください。
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/zCV9U53YHr0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
多くのお子様のお越しをお待ちしています。(栗原)
7月21日(土)9時30分~県庁昭和庁舎21会議室にて
公認会計士・税理士の「福田 秀幸」さんを講師にお迎えし
「NPO法人会計基準」税理士から学ぶ基礎講座を実施しましたので報告します。
講座の様子(午前39名 午後31名参加しました。)
講座概要
Ⅰ.午前の部-基礎編
第1章 NPO法人会計基準の特色
第2章 NPO法人会計基準の構成
第3章 NPO法人が作成する財務諸表
第4章 勘定科目の設定
(質疑応答・昼食休憩)
Ⅱ.午後の部1-応用編
第5章 現預金以外に資産・負債がある場合
第6章 特定非営利活動に係る事業とその他の事業を行っている場合
第7章 NPO法人に特有の取引等
第8章 従来の方法からの移行
Ⅲ.午後の部2 税務編
税第1章 法人税
税第2章 消費税
税第3章 源泉所得税
(本日のまとめ・質疑応答)
基礎編のまとめ
①会計報告書は「活動計算書」「貸借対照表」「財務諸表の注記」+「財産目録」
②お金の入出金を表す「収支計算書」からサービスの発生した時点で収益・費用を
計上する「活動計算書」へ変更
③活動計算書の一番下の「次期繰越正味財産額」と貸借対照表の「正味財産合計」
は一致する
④現預金以外に資産・負債がなければ、現金主義の収支計算書と活動計算書は一致する
⑤NPO法人会計基準は複式簿記が前提だが、多桁式の現金出納帳は複式簿記の
簡易版である
⑥活動計算書は「経常収益」「経常費用」「経常外収益」「経常外費用」に分ける
⑦勘定科目については、会計基準の「別表1」に活動計算書の科目、「別表2」
に貸借対照表の科目を例示
⑧経常費用は「事業費」と「管理費」に区分したうえで「人件費」と「その他経費」
に分ける
⑨事業費は事業の種類別ではなく支出の形態別に分類する
⑩事業費と管理費の按分は、まず、管理費とは何か?を明確にした上で、事業費と
管理費に共通する経費は従事割合等により按分する
⑪収益の部は、「受取会費」「受取寄付金」「受取助成金等」「事業収益」
「その他収益」の5つに分ける
⑫スタッフが経費などを立替払いをしており年度末にまだ精算していない場合には、
未払金を計上する
応用編:第5章まとめ
①「活動計算書」は、活動を表す計算書なので、お金の入出金時点ではなく、
サービスなどが発生した時点で計上する
②日々の記帳から発生した時点で計上しなければならないわけではなく、日々の
記帳はお金の入出金時点で計上し、年度末に入出金とサービスの発生がずれて
いるものだけ計上することも可能
③年度末時点で、活動は終わっているが、未入金の場合、まだ支払っていない
場合は、「未収金」、「未払金」に計上する
④すでに仕入れ又は製作をしたが、決算までにまだ販売していない在庫がある
場合には、「棚卸資産」に計上する
⑤建物や車のように何年にもわたって使うものは固定資産に計上したうえで、
毎事業年度、減価償却費を計上する。
⑥いくらから固定資産に計上するかは、法人の内部規定等で決めればいいが、
法人税法なども参考になる
⑦複数の事業を行っている場合には、財務諸表の注記で、事業費の内訳を表示
する方法と、事業別の損益を表示する方法のいずれかを採用することができる
応用編:第6章・第7章まとめ
①特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行っている場合には、
活動計算書は必ず区分して表示するが貸借対照表を区分するかどうかは法人の任意
②現物寄付を受けた場合には、公正な評価額で、「受取寄付金」として活動計算書
の収益に計上をするとともに、貸借対照表に資産として計上する
③無償等による物的サービスの提供を受けている場合やボランティアの受入れを
している場合には、原則としては会計上認識しないが、金額を合理的に算定できる
場合には財務諸表に注記、金額を外部資料等により客観的に把握できる場合には、
活動計算書に計上できる
④使途が制約された寄付金等は、原則は活動計算書に収益に計上したうえで、
「注記」に明細を記入する。
⑤助成金・補助金については、事業の実施に応じて収益に計上する
応用編:会計基準導入にあたって検討すべき事項
①勘定科目名はどうすべきか?
②何を事業費と考え、何を管理費と考えるか?
③事業費と管理費に共通する経費をどう按分するか?
④複数の事業を行っている場合に、どのように事業を表すか?
⑤複数の事業に共通する経費をどう按分するか?
⑥記帳の方法をどうすべきか?
⑦ボランティア等を把握する仕組みを作るか?
写真は例題の回答です。参加された皆様、確認願います。
写真は司会の峯岸です。
次回は8月28日(火)13時~県庁昭和庁舎21会議室にて
日本ボランティアコーディネーター協会運営委員の
「妻鹿 ふみ子」さんを講師にお迎えし
「コーディネートの力」:20120828megasann.pdfをダウンロード
を実施しますので皆様の参加、お待ちしています。(栗原)
中間支援組織支援力強化事業2012(NPO支援のための連続講座 第7回)
を実施しましたので報告します。
日時:平成24年7月11日(水)14:00~16:00
会場 :県庁昭和庁舎21会議室
講師:徳永 洋子さん 日本ファンドレイジング協会事務局長
テーマ:地域に善意の資金循環を
(講義開始に当たり)
最初に、日本ファンドレイジング協会の夢・希望をお話しいただ来ました。
・日本の寄付を1兆円にしよう!
・未来の寄付者を教育しよう!集めよう!
など。
参加者が「考えてみよう! NPOのスゴイところって・・・?をテーマに」
隣同士で5分間、自己紹介を兼ねて話し合いを実施。

(講座の様子と講座概要)



〇NPOのスゴイところって・・・?
・地域コミュ二ティ=地域内の自発的につながりをもって関わりあっている
人たちから構成される集合体
・行政(官)企業(民)住民(私)をつなぐのが地域のNPO
・地域コミュニティのプラットフォームとして、各NPO自身が社会との
コミュニケーションに努めて、その価値を伝えていく必要がある。
〇個人とつながる魅力的な寄付集め
①ネーミングによる魅力
例:熊本城復元募金 1万円で 「一口城主」
②バリューをつなげる
例:TABLE FOR TWO
③何円で何ができるかを明確化
④一口いくらという設定
例:NPO法人日本グッド・トイ委員会が運営する「東京おもちゃ美術館」
⑤モノ系の入りやすいメニューを用意
⑥ゼロ円で出来る寄付
⑦デザイン・シンボルで訴求力UP
例:NPO法人難民を助ける会
⑧寄付者をたたえる
例:熊本城の復元された天守閣内(熊本城復元募金)
⑨楽しみながらできる寄付
例:One Beer,One Book
⑩記念日の寄付
例:NPO法人高知市民会議
〇企業とつながる5つの類型と事例
①コーズプロモーション
自社で特定の社会課題についての認知拡大や寄付集めの
キャンペーンを行うもの
例:JALの機内でのUNICEF募金
イオンの「幸せの黄色いレシートキャンペーン」
②寄付付き商品
売り上げの一部が寄付になる商品やサービスの販売
③ソーシャルマーケティング
自社で特定の社会課題について、社会に具体的な行動を促す
キャンペーン。
例:ワコールの乳がん撲滅「ピンクリボン・フィッティング
キャンペーン」。キャンペーン期間中にブラジャー試着
1枚ごとに財団法人日本対がん協会の「乳がんをなくす
ほほえみ基金」に10円を寄付
④コーポレイト・フィランソロピー
NPOなどへ直接の寄付を行うこと。伝統的な企業の社会貢献。
例:震災時には、NPOを通じて被災者へ物資を届けたことで、
企業にとっては、マナーリスクの軽減にもつながった。
⑤社会的責任に基づく事業
本業を活かして特定の受益者に対して技術や商品を提供すること。
例:BOP(Bottom of Pyramid) を対象として、ユニリーバは購入
しやすい小袋入りの石鹸をインドで商品開発した。NGOを通じ
て配布するだけではなく、それを現地の女性たちが販売する
ことで自立支援にもつなげた。
ベッドメーカーの要介護者向けの介護ベッドの提供。
〇行政とつながる
コミュニティファンドに期待される2つのこと
①コミュ二ティファンドの資源調達の過程で、地域でどんな問題が生
じているのかわからない、その課題解決にどう参画していいかわか
らない人たちが「社会の課題解決に参画するはじめの一歩」を踏み
出すきっかけとなり、そこから地域の課題やその解決に取り組む
NPOへの関心を深めていくことが期待される。
②その資源が、コミュ二ティの基盤を強化し、地域社会における課題
を解決し、地域を活性化する
例:犯罪減少、高齢者・障害者の生活支援、子育て支援、青少年育成
=行政コストの削減 地域経済の成長
〇コミュ二ティファンドの原資調達プレイヤーの果たす役割
①行政の役割
機会の創出(イベント・広報)
信頼性の確保(情報の一覧公開)
②NPOの役割
期待値の向上(活動実績・成果の可視化)
達成感の提供(支援者コミュニケーション)
〇原資の調達として期待される2つのもの
①寄付付き商品
地域の商品・サービスを消費することが寄付になるということで、
地元企業や商店街を巻き込みやすい
②遺贈
少子高齢化のなかで「地域への恩返し」の受け皿となる
◎ファンドレイジングの基本
問題への共感
×
解決策への納得
+
信 頼
↓
支援⇔成功体験
地域コミュニティに 善意の志金循環を!
(講座後隣の人と講座の感想を話合っていただく)
・皆さん話が始まると中々終わりませんでした。
(質疑)
・講師から丁寧に質問にお答えいただきました。
次回は7月21日(土)9時30分~県庁昭和庁舎21会議室にて
「NPO法人会計基準」税理士から学ぶ基礎講座
①NPO法人会計基準の使い方誰でもわかる基礎編
②NPO法人会計基準の使い方
問い合わせ: NPO・ボランティアサロンぐんま
電話:027-289-3399 FAX : 027-210-6217
E-mail gunma-nposalon1@kl.wind.ne.jp
ブログhttps://nposalon.kazelog.jp/npo/
を実施しますの、皆様の参加をお待ちしています。(栗原)
中間支援組織支援力強化事業2012(NPO支援のための連続講座 第6回)
を実施しましたので報告します。
日時:6月28日(木)13:00~16:00
会場 :県庁昭和庁舎21会議室
講師:森 良 さん NPO法人 エコ・コミュニケーションセンター代表
講義:「相談対応」 + ワーク
(概 要)
1.参加者同士の自己紹介:アイスブレーキング

(不特定の人々が集まる場で、お互いの警戒心を解き、心を開き楽しく
していくための手法や、コツです。)
今回は一人一人が握手しながら自己紹介を実施
2.講義概要
(1)日頃から心がけておくこと、大事なこと
・書いて残す
・大事なところにマークを付ける
・キーワードを見つける
⇒⇒⇒ここから質問する。
(2)問題・課題が出てきても、即アドバイスをしないこと。
・答えは自分の中にある。
・その答えを引き出してやる。
・話だけだと消えてなくなる。
(3)人生の棚卸
・小学校・中学校・高校・・・いま・・・
将来①良くなる、将来②悪くなる
・出番と居場所:先輩の話を聞いて、やりたいことをまとめる
・反応・
話すことで楽になる、交通整理をしてやれば一生懸命聞く
3.ワーク:相談対応のロールプレイ

(目 的)
・相談内容の本質をつかむために、「しっかり聴く力」を高めます
・解決に向けた方策を検討するために必要な情報を引き出したり、
相談者の頭を整理するために、「質問する力」を高めます
・実際の相談内容に、解決の糸口を提供します
(進め方)
・準備
3人一組のグループをつくる
A:コーディネイター(聴くひと)
B:相談者(話すひと)
C:オブザーバー(観察するひと)を決める
(ロールプレイ+観察)10分
A:Bの相談に耳を傾け、できるだけ課題のありかや背景、解決の
可能性などを見出すために質問をしながら状況を把握する
B:Aに自分の活動において悩んでいることを相談する
C:二人のやりとりを観察し、観察シートに気づいたことを記録する
(3人で問題解決)5分
A:Aは、Cを交え、Bの悩み解決に向けた情報を引き出したり、B・Cの
対話をサポートする(ファシリテーターの役割)。
また自らアドバイスも行う
C:Bの悩み解決に有効な情報を提供する
(フィードバック)5分
C:20分間のA・Bのやりとり(とりわけ最初の10分のAの態度や発言)
について、気がついたこと(よかった点、気になった点、改善
方法など)を伝える
*:上記を1ラウンドとし、役割を変えて、3回行う(Cがタイムキーパーを行う)
(観察のポイント)
A:「聴くひと」については、こんな点に気をつけて観察しましょう
・どんな態度で聴いているか?
・どんな質問をしているか?
・自分ならどんな質問をするか?
B:「話すひと」については、こんな点に気をつけて観察しましょう
・課題は何か?
・自分が提供できる情報はないか?
4.振り返り
司会の峯岸です。
次回は「資金調達支援で自己資金開発と市民ファンドの動き」です。皆様の参加お待ちしています。(栗原)
中間支援組織支援力強化事業2012(NPO支援のための連続講座 第5回)
を実施しましたので報告します。
日時:5月25日(金)13:00~17:00
会場 :県庁昭和庁舎21会議室
講師:川北 秀人 さん IIHOE[人と組織と地球のための国際研究所] 代表者
講義:「活動・組織運営を支援する7つのチカラ」 + ワーク
(概 要)
NPOの支援は、なぜ、どのように行われるべきか? NPO支援の意義と機能を再確認する
1.相談対応力
2.調査・情報収集力
3.編集・発信力
4.コーディネート・ネットワーキング力
5.資源提供力(人材・物品・資金)
6.内部の人材育成力(スタッフ・理事)
7.政策提言力
ポイント
①NPOは「1歩先の視野・半歩先のプログラム」
②中間支援は「2歩先の視野・1歩先のプログラム」
写真は、講座の様子です。
写真はワークの様子です。
写真は他班の「方針」にコメント+投票しているところです。
写真は司会の峯岸です。
(講座の概要)
自分がこの仕事に取り組もうと決めた17年前、個人を支援する組織
(機能)はあったが、組織を支援する組織は無かった。
・相手の団体の目的は何か?
・相手の活動の対象や期待される機能を、わかって支援しているのか?
・相手が必要なもの、良い成果が出せるために何が足りないのか?
・今、何が足りないのかも必要だが、次に何が足りなくなるのか?
・ちょっと先に何が起こるのか?その一歩先を見て、次に何をするのか
予測ができていないと。
・ボランティアのマネジメント:どんな成果を引き出してもらう?
・時間を大切にした会議ができるかどうか?
・会計を適切に使っている情報が出せるかどうか?
⇒大きくなれない。
NPO支援センターの現状 総数400以上?
・日本NPOセンターの354か所リスト(10年)によると
設立者:民間77、社協11、自治体268(75%)!
県庁所在地市以外にも211(全施設中59%、全市中25%)
・NPO・市民活動支援センターの本来的な使命は、
「市民活動の支援」か、「地域の課題解決と理想実現」か?
・社協ボラセンの本来的な使命は
「ボランティアの活発化」か「地域福祉の充実」か
2020年に、どんな社会を実現したいか?
「年間事業(目標)額」と「活動開始後の年数」:表で説明
・年間事業額(または目標額)を、
0~300万円~1000万円~5000万円以上の4段階に分類。
・団体の目標と現状との差(=課題)に応えているか?
・そもそも団体が「社会における役割」を意識しているか?
支援センター = 病院
・教える・場を与えるのではなく、課題を解決し、理想を実現する
・求められる基本的な機能は
・緊急救命(ER)
・治療
・予後(+健康増進)
・予防:予防研究、予防広報、予防行動
・身近にかかりつけの診療所、広域で総合病院
・来訪者だけが利用者ではなく、
本当に必要な人のもとに「往診」する!
「支援」とは (支援センターが持つべき7つのチカラ)
・相談対応力
・調査・情報収集力
・編集・発信力
・コーディネート/ネットワーキング力
・資源提供力(人材、物品、資金)
・内部の人材育成力(スタッフ、理事)
・政策提言力
支援者として責任と役割を果たすには
「誰を、なぜ、どう支援するか」を定め、
相手のビジネスモデルを確認したうえで、
・相談対応:質問に答えるだけでなく、予測して発信する
+ 質問と答えを一般化し、研修・機関誌などで共有する
・調査・情報収集:団体の代わりに情報を収集・提供する
+ 住民・企業・行政を動かすために情報収集・提供する
・編集・発信:分析し、相手にもメディアにも役立つ整理を
・コーディネート/ネットワーキング:互いに役立つ接点を
・資源提供(人材、物品、資金):ボランティアや助成金より
インターン、貸出・中古譲渡・割引、寄付付き販促(CRM)
・内部の人材育成(スタッフ、理事):広く通用する専門性を
・政策提言:自他ともに総合評価+影響を予測して提案する
団体から集めるべき情報?
・組織図
・意思決定のしくみ・流れ
・人材育成のしくみ
・現場での工夫・すごさ
・自分たちでは気付いていない課題
「施設を管理するチカラ」は?
・使いやすさ&使い心地よさ
・配置、備品、図書、
・トイレ、駐車場、
・段差、空調、音、
・表示、展示、企画、収蔵、
・ルール、書式、
・整理、整頓、清掃、姿勢、しつけ(5S)
・リスク・マネジメント
・困った利用者への対応
・災害時などの対応
・犯罪・不法行為への対応
誰に、どう使ってもらうか?
・ハードの利用を促進するために?
・会議室には、「会議のもっといい方法」紹介
・印刷機には、「すてきなチラシ・機関誌コレクション」や
「こういうところに情報を送ったら?」リスト
・壁に貼った情報には、同種のイベント・団体に誘導を
・世の中の話題に連動した、「オススメ資料」展示
・ソフトの拡充と活用を同時に促進するために?
・「薬箱」 → Q&A形式でノウハウを提供する
・「こんなときどうしてますか?」情報ボード
(以下ワークで実施)
どんな質問・相談に答える?(各自4件の質問を作成)
・過去に寄せられた「質問・相談」で、他人の意見を聞きたい
悩んだもの など
・これから来そうな、(or訪問時に備えたい)質問・相談
(3~4人でグループとなり、各自の質問・相談を説明)
10問10答をつくる(グループ内で10問を選択)
各質問ごとに
・考えられる原因・背景
例:手法・手続きを知らない?
流れの設計が不十分?
つまづきの初期対応?
判断時の確認不足?
・相手に確認すること
・・・したことがある?
・・・できなかった経緯?
決めたあとに・・・した?
・・・・・・・・・・・?
・答えの流れ
まず・・・してみては?
→次に、・・・・・・・
→そのうえで、・・・!
他班の「方針」にコメント+投票する
・緑色のポストイットで
相手に貢献する
質問、助言・提案
・青色のポストイットで
投票(理由)
「ここがいい」 「この部分が参考菜なった」
「ビジネスモデル」とは?
・誰に、何を、いくらでていきょうするか
・顧客をどれだけ分けられるか?
・収入をどれだけ多様化できるか
・利用者・参加者だけでなく支援者・協力者も
・期待を上回る価値か?
・健全な自転車操業もアリ!
ふりかえり
・この研修で気づいたこと
・学んだこと
・こころに残った誰かの言葉
(参考)IIHOE紹介
組織目的: 地球上のすべての生命にとって、調和的で民主的な発展のために
社会事業家(課題・理想に挑むNPO・企業)の支援
隔月刊誌「NPOマネジメント」発行
育成・支援のための講座・研修
地域で活動する団体のマネジメント講座(年100件)
行政と市民団体がいっしょに協働を学ぶ研修(年40県市)
企業の社会責任(CSR)の戦略デザイン
ビジネスと市民生活を通じた環境問題の解決
2020年の地球への行動計画立案
専従3名+客員1名、東京(新川)
次回「NPO支援のための連続講座 第6回」は
6月28日、県庁昭和庁舎21会議室にて
テーマ:相談対応
講師:「森 良」さん(NPO法人 エコ・コミュニケーションセンター代表)を
実施しますので、多くの皆様の参加をお待ちしています。(栗原)