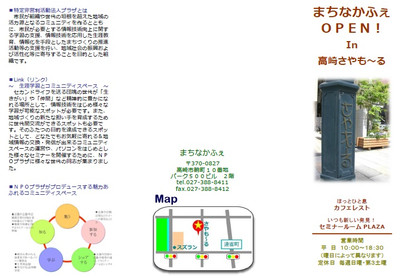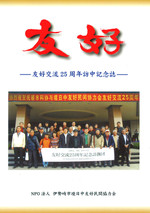特定非営利法人 群馬わんにゃんネットワーク
理事長の、飯田 有紀子さんにお話しを伺いました。
現在日本のペットブームの中、動物愛護の精神に於いて先進諸外国に
大きく遅れている現状は否めない。
動物・飼い主・地域住民のより良い暮らし応援する為の情報提供、啓発
活動に努め、見捨てられた動物の譲渡支援にも取り組み、子供たちへの
命の大切さ・動物愛護への気風を招来し、動物への理解と愛護の精神を
広める事を目的として設立されて1年だそうです。
取材させて頂いたこの日は、譲渡会。 6匹のわんちゃんが新しい家族を
待って居ました。私が驚いたのは、譲渡審査の厳しいことでした。
始まる30分も前から待って居た男性に対し『飼いたい気持ちが貴方だけ
でなく、家族全員が一致していないと譲渡は難しい!来週ご家族でお出で
下さい。』この言葉の裏には、動物たちに対する愛情と、来て下さった方へ
揺るぎない気持ちの確認を頂く時間をさしあげる。大きな愛を感じました。
上記の写真は、新しい家族 高崎市のKさんとミルちゃんです。
ボランティアの方も加わり幸せな笑顔。皆さん、この笑顔の為に頑張って
居られる事がわかりました。私までが幸せな気持ちになった1日でした。
心あるご家族の来館を心からお待ちしております。 (鈴木)