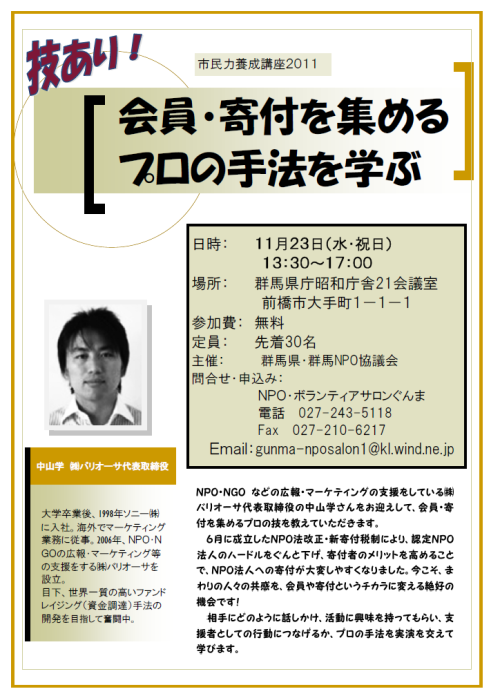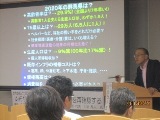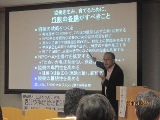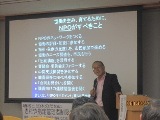第20回全国ボランティアフェスティバルTOKYOが、11月12日(土)13日(日)に行われました。両日にわたって、63の分科会が開催されましたが、その中の一つである「TOKYO油田と下町ツアー」に参加しました。
当日はTOKYO油田プロジェクトリーダー・株式会社ユーズの代表取締役である染谷ゆみさんに、楽しく案内をしていただきました。

両国国技館を出発して
↓
ペットの墓も多数あるという回向院
↓
現在ベネチア展開催中の江戸東京博物館
↓
東京大空襲で墨田区一帯は10万人が犠牲になったそうで、関東大震災・太平洋戦争犠牲者の遺骨をあわせて安置している横綱町公園(東京慰霊堂)
↓
地方からの参加者が多かったので、見える度に歓声が上がった東京スカイツリー
↓
墨田川・荒川
↓
逆さツリーが水面に見える十間川。
下町は道路が狭くバスが止められないということで、以上のポイントは全て車中から眺めました。
そしてほどなく染谷商店・TOKYO油田(株式会社ユーズ)に到着しました。


ここでは使用済みのてんぷら油を回収して、リサイクル工場で再資源化することによって、資源循環型の社会づくり・地域づくりの実現を目指しています。BDF(バイオディーゼルフューエル)のパイオニアです。
使用済み天ぷら油をリサイクルする工場と、油をためておくタンク


2017年までに、東京都の天ぷら油を一滴残らず回収して、eco資源へを合言葉に活動しています。
TOKYO油田2017プロジェクト
http://tokyoyuden.jp/
一行はまたバスに乗り込み、特に住民から反対運動もなく建設されたという墨田清掃工場を車中から眺めた後、梅鉢屋さんに向かいました。



バスから降りて、下町の伝統のお菓子、江戸より伝わる砂糖漬の野菜菓子を試食させていただきました。
見た目もとても美しく、上品な味がしました。贈答品として大変喜ばれるそうです。


梅鉢屋
http://umebachiya.com/
バスの中では、染谷さんが出演したTV番組のビデオを見せていただきました。使用済みの油を各ポイントで回収していますが、お煎餅屋さんに持っていくと、お煎餅が1枚もらえたり、お花屋さんに持っていくとお花が一輪もらえたりと、暖かさを感じる映像でした。
地域の歴史や特色、伝統と新しいものの混在、実際に足を運ぶことで、エコプロジェクトを立体的に捉えることができ、有意義な90分のツアーでした。
ちなみに群馬のBDF情報はこちらから
http://blog.goo.ne.jp/fuuko22
(伊藤)